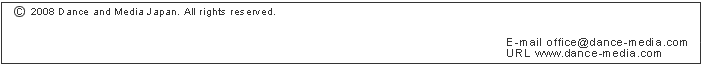〜劇作家とメディア・アーティスト〜
他にもオモシロイ作品は沢山あるのですが、「ポスト・シアター」について少し説明しておくと、ドイツ人劇作家のマックス・シューマッハさんと日本人メディア・アーティストの棚橋洋子さんの二人を中心として、ベルリンとNYを拠点に活動しているユニット。
「ドラマトゥルク」という肩書きは、日本ではまだマイナーですが、マックスさんは「ドラマトゥルク」担当。つまり、コンセプトや物語などの構築を行う人。そこに、メディアアートとの擦り合わせを棚橋さんと進めていく作業です。
以下、ポストシアターのコンセプトからの抜粋。
『演劇においてのインタラクティブ・メディアについて考えよう。』をスローガンにポストシアターは演劇とインタラクティブメディア・アートという二つの全く異なる分野の境界線を越えたところでの作品作りに励んでいます。
その際に『インタラクティブ』という言葉をポストシアターは以下のように定義しています:
▼デジタル・ツールを用いた機能としてのインタラクティブ性
(展示品としての面白み、鑑賞者の作品との外的接触)
=インスタレーション等
▼対鑑賞者と作品との物語の共有としてのインタラクティブ性
(「感動」「想像力」「好奇心」等の 鑑賞者の作品との内的接触 )
=演劇空間
以上の2点をふまえてポストシアターは常にテクノロジーの使用がいかにストーリーとの関係のなかで正当化されているかということに注目しています。発達したテクノロジーは演劇という分野の可能性を無限に広げていきます。同時に、演劇がテクノロジーの奴隷となって、テクノロジーを見せる為だけのマルチメディアショーとなることも稀ではありません。テクノロジーをただの効果として使用するのではなく、『どのテクノロジーがどこに、どうして設置されているのか?』ということをストーリー設定に盛り込みながら、作品をつくっていくことで、より強化なテクノロジーと演劇のシナジーが生まれると信じています。
(抜粋ここまで)
〜毎月どこかでポストシアター〜
ポストシアターの今年の予定を聞いてみると、ほとんど毎月どこかの国でパフォーマンスやインスタレーションをしています。アジア、ヨーロッパ全域。
どれも自主公演ではなく、主催者がいる公演。作品がちゃんと売れている証拠です。
なかなか日本では難しいかもしれませんが、作品を売るということでカンパニーを運営していけると、ストレスも多少軽減するかもしれません。
|