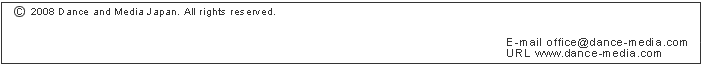■ソフト・アーキテクチュアとは
|
|
|
「建築文化」1970年1月号
「ソフト・アーキテクチュア」の最初のページ
|
ソフト・アーキテクチュアという言葉は、建築家の磯崎新氏が70年代最初に「建築文化」(1970年1月号「ソフト・アーキテクチュア/応答場としての環境」)という雑誌で発表したものです。「大阪万博お祭り広場」(1970)、「エレクトリック・ラビリンス」(1968、ミラノトリエンナーレに出品したが会場が学生運動により占拠閉鎖され未公開に終わった)という二つの作品、ともに当時は画期的だったセンサリングシステムを用いた先駆的な作品を手がけた磯崎さんが、建築・都市空間に対して打ちたてたビジョンがソフト・アーキテクチュアです。それまで物理的に構築されるというイメージが強かった建築や都市に対して、より現象や変化という要素を重視したデザインの可能性があるはずだという内容の論文です。当時はまだコンピューターといえばパンチカードを使った巨大なマシンしかなく、5つのセンサリングをするためには、その巨大なやつが5台必要だという、そういう時代でした。テクノロジーが未発達だったためにかなり想像力を膨らませて構想された、冒険的な論文だったと思いますが、今読んでもそれほど時代の変化を読み間違っていなかったし、けっして古く感じない。こんな内容です。
(余談になりますが、僕が大学院のときにつくったアートユニットResponsive Environmentという言葉も、実はこの文中に出てきます。実は、ユニット名をつけたとき僕はこの論文の存在を知りませんでしたので、あとから偶然にも発見して驚いたという経緯もあります。)
引用 -
「つまり、建築はソフトウェアを含むことによって、不可視の部分の占める割合が増大し、さまざまな新しい環境を決定づけるメディアによって、活動が遂行されるものになる。さらに全都市的に活動が拡散していくことによって、都市と一体化し、都市内に溶解してしまう。かくして、建築が都市となり、都市は建築そのものになるという言い方が可能になり、都市=建築という環境を設計することが、大きい課題になってくることが予想されるのである。」(前出書)
磯崎さんのソフト・アーキテクチュアの定義のようなものはこうです。
「建築は環境を決定づけるメディア自身になるのである。ここでは、建築の意味が多様化し、存在が無定形化し、時間軸に沿った演出的なものになり、まったく流動化してくる。これを制御することが建築の中心的な課題になることは明らかで、建築はソフトウェアを当然ながら包含する。そしてさまざまな情報がとびかい、発生しているなかにはいりこむ人間の行動と応答するような諸装置をつくりだすことが、技術的な解法の目標となる。こんな建築を、ソフトアーキテクチュアと呼ぶことにする。」
ここではソフトウェアによって都市や建築の境界が曖昧になるだろうということが予言されているわけですが、こうしたことが、現在、建築・都市デザインの分野で現実に起こり始めているというのが僕の実感です。僕は、REで発表してきたような小さなアート作品やパフォーマンスから建築のデザイン、アーバンデザインまでいろいろなスケールの空間デザインをまったく区別せず、同時に行うことにしています。小さなアートプロジェクトやパフォーマンスのためのアイディアが、発想を変えると、巨大なスケールを持ったアーバンデザインにも応用できるのではないかと考えているからです。
■インスタレーション/コラボレーション/パフォーマンスという3つの手法
僕は、空間デザインを、スケールに関係なく展開できるのではないかと考えていますが、そのために重要になってくるのがインスタレーション、コラボレーション、パフォーマンスという三つの手法です。これはREを結成した当初、自分たちがこれから行う活動の特徴を示す言葉として挙げていたものでが、最近、改めて、これらをそのまま、これからの建築・都市デザインの可能性を表す言葉として使えるのではないかという気がしています。REは1993年に結成され、いろいろなメンバーが集まってコラボレーションしながらインスタレーションやパフォーマンス作品を作ってきました。活動の特徴をひとことで言えば、時間に沿って変化する空間的な作品をつくってきたといえると思います。われわれがそこで体験してきたデザイン手法がアートや舞台の分野だけでなく、どのように建築や都市デザインの分野にまで応用可能かということについて考えてみたいと思います。
■インスタレーション
インスタレーションという言葉は、アートの分野で1970年代に使われるようになったといわれています。それまでの台座や額縁とセットになって作品そのものとして完結したアートから、美術館や屋外空間などをつかって、その固有の空間を活かしながら環境自体を作品として提示するという動きを表します。
 |
 |
|
再製作されたElectric
Labyrinth @ZKM「Iconoclash」展にて
(撮影:SLOWMEDIA 日高)
|
僕は、磯崎さんから依頼されて、2002年にドイツ、カールスルーエにあるメディアセンターZKMで、「エレクトリック・ラビリンス」の再制作を行いました。この作品は、幅約12m、奥行約15m、高さ約4mという大きな規模のもので、ミラノトリエンナーレの会場の1室全てを使って展開したものでした。70年代にブームとなったインスタレーション・アートのはしりだともいえます。(その後、日本では「Expose2002夢の彼方へ」展においてキリンアートプラザ:2002年、横浜赤レンガ倉庫1号館:2003年にて展示が行われた。また、イタリア、ポルトガル、中国、ロシアなどの国も巡回)
再制作の準備のために文献をあたるなかで、先に挙げた70年の磯崎さんの文章に出会い、ソフト・アーキテクチュアというコンセプトについて知りました。その後しばらくしてから、磯崎さんのコンセプトを現在のテクノロジーで展開させたいと考えるようになり、REで「ソフト・アーキテクチュア」という一連の作品を作り始めます。これは、プロジェクトが始動した当初につくったウェブサイトhttp://www.slowmedia.net/softarchitecture/
です。この頃は、特にプロジェクションを使って、立体映像をどうやってつくるか、ということスタディしていました。その後、同じソフト・アーキテクチュアというシリーズでも、少し違った展開をしています。例えばSOFT
ARCHITECTURE @1929(2006年3月、横浜バンクアート1929)では既存の空間をそのまま使って、照明と音楽とひとりのダンサーだけで空間を演出するなど、映像システムを使わない作品も発表しています。

Responsive Environment「Garando」
(撮影:日高 仁)

Responsive Environment「SOFT ARCHITECTURE
@1929」
(2006年3月横浜BankART1929hall、撮影:日高 仁)
エレクトリック・ラビリンスもそうですが、建築家がアートの分野で活動するとき、インスタレーションという手法はとても自然な展開だと思います。もともと建築家は空間そのものをテーマとして扱っているので、その作品が設置される空間に立って、そこから発想する結果、その空間固有の作品が生まれるケースが多いからです。REでは、たとえパフォーマンスの舞台を作る場合であっても、パフォーマンスをやっていないときの空間が、インスタレーション作品として存在するようなものを作るようにしてきました。
インスタレーションとは、既存のスペースを尊重し、それに対して「介入」していくという手法だと思います。また、そのとき同時に、最小限の介入で最大の効果を生むことを目指します。そこには常に、既存の空間との呼応関係があります。
建築や都市のデザインをする際にもやはり、周辺のコンテクストや人々の活動など様々な要素に対して介入していくこととなるため、インスタレーションと同じ発想が有効です。
■コラボレーション
REを始めた90年代は、実はパソコンが僕たちの手に届くようになった時期でもありました。最初は、建築家、音楽家、ダンスの振付家などを志す学生が集まって始めた活動でしたが、コンピューターのソフトウェアが活動分野の異なる僕たちの共通言語として機能していました。実際その可能性に気付いたのは遠藤拓己という当時のメンバーが音楽家なのに非常に素晴らしいCGパースを、見よう見まねで覚えたという3Dモデリングソフトを使ってつくって持って来たときでした。それ以来、REでは共通のルールとして、専門分野に関わらず各自がトータルな提案を行うようになりました。そのころは、まだコラボレーションという言葉は比較的目新しかったのですが、何となくこういうことかと実感しながら僕たちは使い始めました。
都市や建築は、それをつくるのに非常に多くの人々が関わるという意味で、必然的にコラボレーションによってつくられるといえます。もちろん、過去には独裁者によってデザインされ、構築された巨大建築物や街も残されていますが、近代以降の民主社会ではそれ自体ほぼ不可能になりました。かわって、産業革命以降起こったモダニズムのムーブメントでは、産業によるテクノロジーを共通言語として建築や都市をつくろうとしました。現在、われわれが手にしたのは、こうした工業技術に加えて、高速化され電子化されたコミュニケーションのテクノロジーです。都市を活動するものとしてイメージするとき、アーバンデザインや都市政策は、都市を経営する行為にかなり近いものとして考えられます。変な例えですが、都市をひとつの会社としてみることもできると思います。そのとき、コラボレーションのかたちは、その会社のワークスタイル、協働でプロジェクトを動かすという会社の活動そのものということがいえます。言い換えればコラボレーションのかたちは、このように都市のあり方そのものに確実に影響を与えるものだといえます。
REの事例に限らず、様々な分野で活動する人々に共通のコミュニケーションが存在するということは非常に重要だと思います。専門的な事柄や、クリエイションの過程で出てくるイメージのやり取りでは、言語が伝えられることは非常に曖昧で、随分ずれがあるということを、我々は、例えば建築家と音楽家が使う日常的な言葉のずれなどから実感させられました。同じことを話して、その場では分かり合ったつもりでも実は全然違うことをイメージしていたという現象が頻発したからです。言語だけに頼らない、イメージやシステムを含む多様なメディアによるコミュニケーションが重要です。さらに、このコミュニケーションのなかから、どう方向性を導き、デザインに結び付けていくかということがキーになります。
現在、僕たちが手にしたのは、例えば隣にいる人も地球の裏にいる人も、同じくらいの頻度でメールや電話でやり取りできる、比較的手軽に移動もできる。そういうかたちのコミュニケーションだと思います。そういうコミュニケーションで、コラボレーションのあり方がどう変わっていくのかというのが、僕の今の関心なんですけども、可能性としては、例えばそれが原因で都市が変わるんじゃないか、と思っています。いままでのアーバンデザインの手法は、敷地の境界線を前提とするところからすべてが始まっています。つまり、まず都市計画というのは、敷地境界をきめることから始まるともいえます。色を塗った地図ができて、その中でさらに細かく敷地を割り込んでいって、ゾーンの用途や建物のボリュームが決まる、という流れです。でも、僕たちのコミュニケーションの可能性について考えると、もうすこしノンスケールに、あるいは場所からフリーに物事が再編成できると思うんです。例えば、普通の人は色分けした地図なんかより隣近所などの身近な風景のほうがイメージしやすいとか。あるいは、東京と沖縄と行き来している人にとって、そこはもうひとつの連続した場所になってきますよね。違う都市間で共同のプロジェクトが走るとか、そういうことが実際にできるんじゃないかと。姉妹都市とか、ああいうほとんど機能していないような仕組みではなくて、本当の意味での連携都市ができるんじゃないか、と思います。
 |
 |
|
UDCK柏の葉アーバンデザインセンター
(2006年11月オープン、撮影:日高 仁)
|
また、別の例えをするならば、我々が話しているUDCK(http://www.udck.jp/)も、アーバンデザインの新しいコミュニケーションのツールとしてつくられています。スペース自体がコミュニケーションのためのメディアだという発想です。
■パフォーマンス
ここでいうパフォーマンスというのは、言い換えれば「時間のデザイン」のことですが、舞台作品のような短い時間の演出だけではなく、もっと永い時間についても同じように考えたいと思っています。
コラボレーションの結果を何らかの形で収束させ、新しいデザインに結びつけることで、例えば都市のような大きな対象をデザインすることは、大変難しいことだといえます。デザインのクリエイティヴな部分を、多数決で見つけていくのは非常に難しいからです。この問いに科学的に取り組み続け、洗練されてきた開発手法を、プロダクト・デザインの分野に見ることができます。それをひとことで言えば、「トライ&エラーとフィードバック」のシステムです。プロダクト・デザインの開発手法はこうです。「いろいろ試しに作ってみて、世に出してマーケットの反応をフィードバックして次のものを作る」。新薬などのデザインにおいては、実験的に敢えてある程度ランダムな要素を加えておき、理論を外れた予想外の結果に期待するということも行います。これは生物の種の進化をモデルにした開発手法です。
この洗練された開発手法に見られるような健全な努力を、都市計画はある意味で避けてきた、やってこなかったんじゃないか、と思います。公共が巨大な投資をするわけだから建前として失敗は許されない。国民の了承を得て進めないといけないから、多数決になるし、エラーなんて言葉を政治家は間違っても口にできない。実際は、エラーばっかりなんですけどもね。
最大のエラーは、計画に時間がかかり過ぎることです。道路一本通すのに、数十年という時間がかかってしまうから、計画当初の責任者が一人も残っていない役所で、今も作らなければならなくて、「もうその道路いらない」ってみんな分かってるけどやめられない、とかね。悪い言い方をすれば博打と一緒で、頑張って賭け続けたから、今止めると全部すってしまう。と、そういうことを、公共がわかってやっているともいえます。
プロダクト・デザインでは、短いスパンでトライ&エラーを行い、そこからフィードバックをかけて、次のプロジェクトを動かしていく。駄目ならキッパリとやめる。ひとつずつ結論を出していく。アーバンデザインもそういう風にしていけば、もっといいところがいろいろと出来てくると思うんですよ。コミュニケーションの話もそうですけども、小さいプロジェクトにして、プロセスベースでモノを考えていくということに可能性があるな、と思います。
UDCKもそうした発想でつくられています。われわれは「都市実験」というふうに呼んでいます。ここで展示されているものは、殆どがまだ決まっていないことです。実際の街を想定して大学や行政、民間の参加者で協議し、そこで出たアイディアを、展示やイベントなどでとりあえずいろいろ発表してみる。だからここで発信されるのは、ある意味でトライ&エラーの集積みたいなものです。それでいいと思っています。
もうひとつ、アーバンデザインで固有の問題として、非常に永いタイムスパンと、価値観の変化ということがあります。価値観について言えば、同時代であっても、例えば渋谷川ってドブみたいだから汚い、蓋をしてしまえという人もいれば、あの裏ぶれた感じがいいんだという人もいて、映画の舞台になったりもする。価値観の多様さゆえに結論が出しにくい。また、別の例えでは、京浜工業地帯というのは、高度発展期に国の最優秀な人たちが一致団結してつくったわけで、それが日本の経済発展を少なからず担っていたわけです。でも、この前シドニーに行って思ったのは、品川、川崎くらいの距離のところに、シドニーではとてもきれいなビーチが残っている。都心居住とサーフィンなどのアクティヴィティが完全に共存しています。ボンダイ・ビーチでサーフィンをしながら、これを東京は失ったんだな、と思いました。ある時代に100%正しいと思って最高の技術で作ったけども、別の価値観で言うと、完全に間違っている、ということも結構ある。この他、首都高速道路など、同様の議論はつきません。アーバンデザインというのはそういうものなんですよね。次の世代に残るというのは、そういう恐ろしさがある。どっちに転ぶか、本当に分からない。でも思考をとめないこと、継続して考えることが大切だと思います。
サステイナブルな社会ということが言われるようになりましたが、これは、例えばひとりの人間のライフタイムを超えたスケールの時間や空間デザインのことだと思います。自分の一生を超えたタイムスケールのパフォーマンスという発想は、魅力的なものだと思いますが、そこには大きな構想と絶え間ないエネルギーやアイディアの投下、フィードバックによる修正が必要だと思います。
最後に、僕が考えている「ソフト・アーキテクチュア」というのは、ひとことで言えば、空間のパフォーマンスです。今考えているいくつかのプロジェクトがあって、そのひとつに建築家の故丹下健三さんの空間をテーマにしたものがあります。彼の最盛期の作品として代々木オリンピック体育館と東京カテドラル(ともに1964)があります。丹下さんの葬儀はこのカテドラルで行われました。その二つをプロジェクトの候補地として、そのスペース自体をソフト・アーキテクチュアの舞台にしたいと考えています。
まだ実現できるかわからないけども、「ダークネス」というサブタイトルをつけています。
代々木も、東京カテドラルも、ストラクチャーがとてもハッキリとした空間です。垂直性の高いスペースで誰にでもわかりやすいダイナミックな内部空間をもっています。これを使って「闇」の空間を作りたい。内部の照明を消し、ほとんど真っ暗にしてしまって、そこに微妙な光だけで演出していきます。微妙な光の残光だけが、観客の目に焼きつくような演出です。闇には、奥行きがどれだけあるかわからない広がりがあります。この闇を体験するための、ガイドツアーをしたいと思っています。建物のなかをガイドが案内して、観客が空間を味わう、というような。スペース自体がハッキリした構造で、猛々しい包容力と広がりがあって、時代の空気や丹下さん本人のイメージとなんとなく重なるんですよね。その空間を闇で包み込んで、その中で改めてそれらと対面するとどういう風に感じるか、ということに興味があります。
|