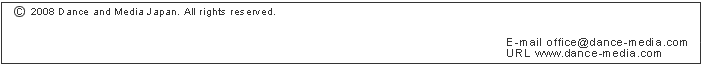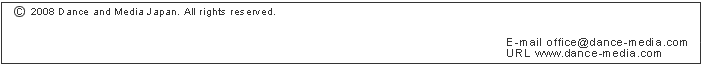|
カンパニー主体のショーケース
この「ショートピース公演」は、Dance theater LUDENSのメンバーによるソロ作品集である。太田ゆかり、伊豆牧子、有吉睦子、梶原暁子、岩淵多喜子の5人が、それぞれ自由にソロ作品を発表した。テーマもスタイルも自由な作品集だ。
作品内容に関する雑感は後述するとして、まずこのイベントの意義を考えてみた。
結論から言うと、ダンスカンパニーという集合体が減っている現在、この企画のようなカンパニー主体のショーケースが増えるといいのになぁ、と感じた。カンパニーが主体となって自分たちのメンバーを売っていく方法として、ダンサーとしての個性や外部のカンパニーへの適応性、柔軟性をアピールするためには、主宰者の振付・演出に縛られない自由なこうしたソロ作品集は有効だ。もしこれがDance
theater LUDENSという看板のないショートピース公演だったなら、イベントとしておそらく何も伝わってこないだろう。一人20分程度の持ち時間で、たとえ同じテーマで共通性を持たせようと企画しても、イベントの強い主旨が見えてこない。しかし「Dance
theater LUDENSのメンバーによるソロ作品集」は、カンパニーの本公演と同じくらいの「ダンスカンパニーとしてのアピール」が伝わってくる。
おそらくスタジオを持っているダンスカンパニーであれば、こうした企画が定期的に行えるだろうし、それはカンパニーメンバーにとっても、クリエイティビティを高める良いチャンスになるだろう。残念ながら東京のスタジオ家賃は高いし、国民に最低限の生活保障も曖昧なこの環境で、アーティストにとってダンスカンパニーの運営は重労働だ。アートマネージメントがちょっとした流行になっている現在でも、即戦力となる制作スタッフをカンパニーが雇用することも苦しい状況。人はいるのに人手不足、という構造になってしまっている。
様々な背景を考えつつ今回の公演を観ていると、粗悪な環境の中でダンスカンパニーが生き抜くガチンコな方法論をDance
theater LUDENSは持っている、ということになる。
ちゃっかりと打ち上げに参加し、そこで岩淵さんに直接話を伺うことができた。
ダンスカンパニーが生き残る道
「自主公演でこうした企画を遂行するのは大変ですよね」という質問に、岩淵さんは相変わらずの凛としながらもフランクに答えてくれた。「やる気になればできるんですよ。お金が無い、時間が無い、というのは、実はわれわれ作り手の言い訳だったりもして、そうならないように活動しないと。」そして「今回、実は初めてソロを作ったんですよ。」と意外な発言。さらに質問。「カンパニーの主宰者はどんどん振付家、演出家になっていき、自分のカンパニーでも踊らなくなっていきますよね。今回のショートピースで若手の紹介だけでなく、最後の岩淵さん自身もソロで登場する、という親分のパワーがありましたね。」それについて岩淵さんは、「自分が最後に、というのも実は段取りの問題でそうなってしまっただけでした。砂を使った作品なので、汚すから、という理由で最後にやるしかなくなってしまって。それと、自分自身初めてのソロなので他のメンバーとは全く同じ立場。一人のダンサーとして登場した、という具合です。」
ダンスカンパニーの親分、という立場と、一人のダンサーという2つの葛藤がみえる。
やはり「ダンス」がおもしろい。

撮影 塚田洋一
|
5作品の中で説得力のあるソロは、やはり岩淵多喜子の『Moment』だ。他の作品が「オーバーラップ」する空間構成を特徴としている中で、『Moment』はシーンが明確に「カットアウト」されていき、独特なスピード感、エッヂ感を感じることができる。
始めのシーン。空き缶に入った砂でラインを描く。寝転ぶ自分の体のラインに沿って砂で線を書いていくシーンだ。動きは非常に機能的で、一筆書きで描くためにちょっとした緊張感が走る。
|
線を描くときに砂の入った空き缶を逆手から、順手に持ちかえる一瞬の動きの「一時停止」が美しい。連続した線を描くために空き缶を持ちかえる、という当たり前の一瞬だが、そこで流れよく持ちかえる動きをするのではなく、「ただ単に必然性があるから、手を入れかえる」という目的と手段の選択が潔い。砂が少なくなって擦れてきたラインで、体育座りをした自分の周りを丸く縁取ると、そこでも一瞬の「一時停止」がある。そこからは、描いた線にもう一度自分の体を当てはめるかのように、シーンの「巻き戻し」が始まる。完全な巻き戻しではなく、砂のラインも蹴散らされ、軌跡が壊されていくエラーがスリリングで、スピードのボリュームが上がっていくシーンだ。
音楽も照明の展開もないこの冒頭のワンシークエンスには、動きの「一時停止」と「巻き戻し」という遡行で、それはターンテーブルでスクラッチをするように、シークエンスの中にいくつかのシーンを立ち現せていた。
これまでにメディアとダンスというテーマで色々なものを観てきて、ダンスに映像、音楽、照明がどこまで必要なのか、ということを考えた。本作を観て明らかなのは、ダンスだけでシーンのカットアウトはできる、ということだ。映像のカットアウトは簡単だ。シーンを切り、次のシーンにモンタージュすればいい。舞台で一番安易なカットアウトは「暗転」だろう。しかし『Moment』のカットアウトは、照明、映像、音楽といった外的要素によるものではなく、ダンスそのもの、動きそのもので生み出していた。
ダンスとパフォーマンスの区分けが曖昧な昨今、「今日はダンスを観た」と確かな実感があった。空き缶と砂という演出に、動きが負けていない。演出過多で「これもダンス、あれもダンス」という拡大解釈でダンスファンを拡張しようとするアイディアも多くなってきた中で、「これがダンス」というアーティスト側からの強度を真っ向から受け取ることができた。こうした硬派で良質なダンス作品が増えるとダンスシーンにもエッヂが戻るように感じる。
Dance theater LUDENS レギュラークラス開講
[日程] 2006年9月〜12月
[会場] BIWAKEIスタジオ
詳しくは、ホームページへ。 http://ludens.at.infoseek.co.jp |