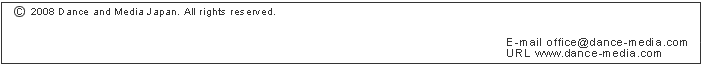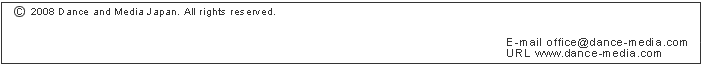|
ダンスにおけるアルゴリズム
以前から「ダンスの最小単位」ということを考える。映画ではよく議論されてきたことだが、映画の最小単位はショットなのか、セルなのか、という議論である。写真の連続である映画は、物質的な最小単位は1枚のセル(一枚の静止画)だ。別のアプローチとしては、ビデオカメラで撮影した作品は映画なのか?フィルムで撮影したものが映画なのか?などなど、色々な考え方があり、決定的な答えはない。
どれも本当っぽいし、どれもどうでもいいことに思えたりもする。実際にその議論はここではあまり重要ではないが、「最小単位」という考え方は面白い。
ウィリアム・フォーサイスが1994年にZKMで制作したCD-ROM『インプロヴァイズド・テクノロジー』には、フォーサイスのダンスメソッドの最小単位が記録されている。
バレエ団のダンサーに自分のメソッドを叩き込み、即興で踊らせてもメソッドに基づいていれば、際限なく踊り続けられるような内容だ。
フォーサイスのダンスメソッドの最小単位は、「点と点を線で繋ぐ」という一つのアクションのように思える。この仕組みの基礎を理解すれば、アルゴリズム的に展開が可能だ。
点を増やす、線を増やす、線を切る、線を繋いで立体を作るなどの展開を、イメージしながら進めていけばより複雑なインプットとアウトプットが出来上がり、即興でも動きに破綻が生じにくい。
ダンス的なアプローチで『CMprocess』を利用する場合には、フォーサイスのように各ダンサーを制御する動きの組み方を共存させるとよいかもしれない。もちろんそうすることによって、本来の『CMprocess』が目指すものとは別のものになるだろう。
しかしシステムは柔軟であるべきだ。「Photoshopは写真を加工するソフトだ」とはいえ、別にイラストを描いてもよい。『CMprocess』をソフトウェアとして利用することは、作品の制作プロセスを考える良い機会となるだろう。
方法論の提示
『水の声』では、能、現代演劇、コンピューター音楽、彫刻というものが同時にステージにあがる。クリスティアン・ツィーグラー氏の作品でも、ダンス、DJ、VJが同じライブでセッションする。そして、CMprocessでは、ダンスだけでなく、都市の中で生じる人の動き、にまで拡大されていく。
元々は「サウンドスケープとパフォーマンス」というテーマで進めてきたワークショップも、単に環境音楽、デジタルメディア、ダンスといったカテゴライズに分けて考えることが不可能なほど、すべてがミックスされていた。
ダンス作品をつくろう、演劇作品を作ろう、という内容的な作業の前に、「物事の考え方」といった根本的な問題提起がされたワークショップになったと思う。
|